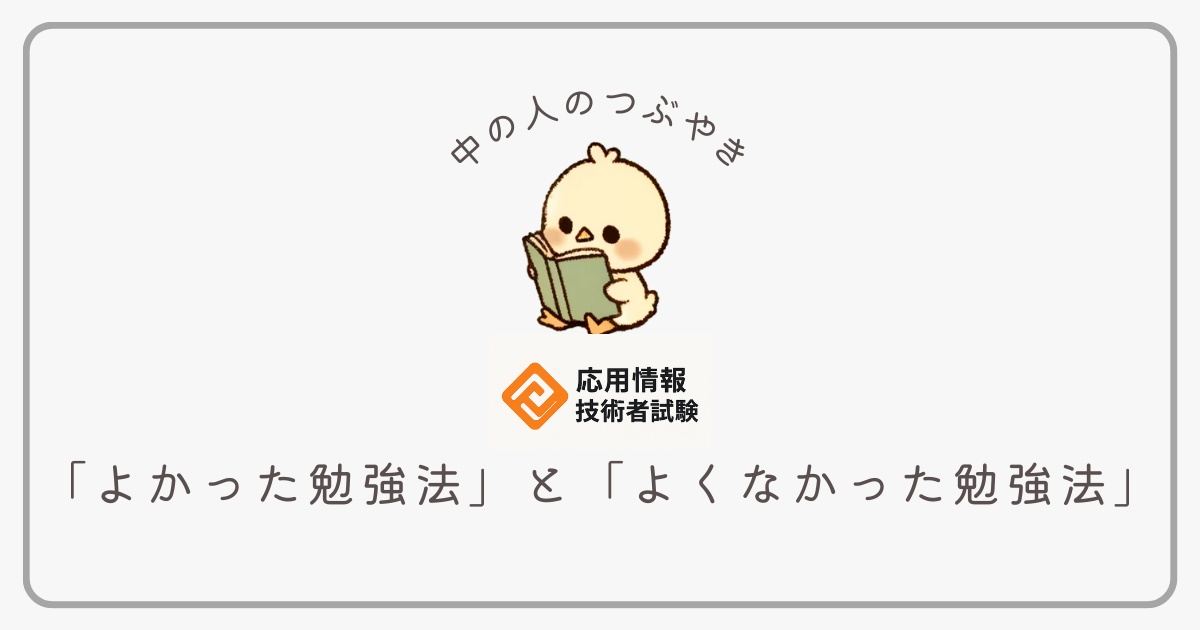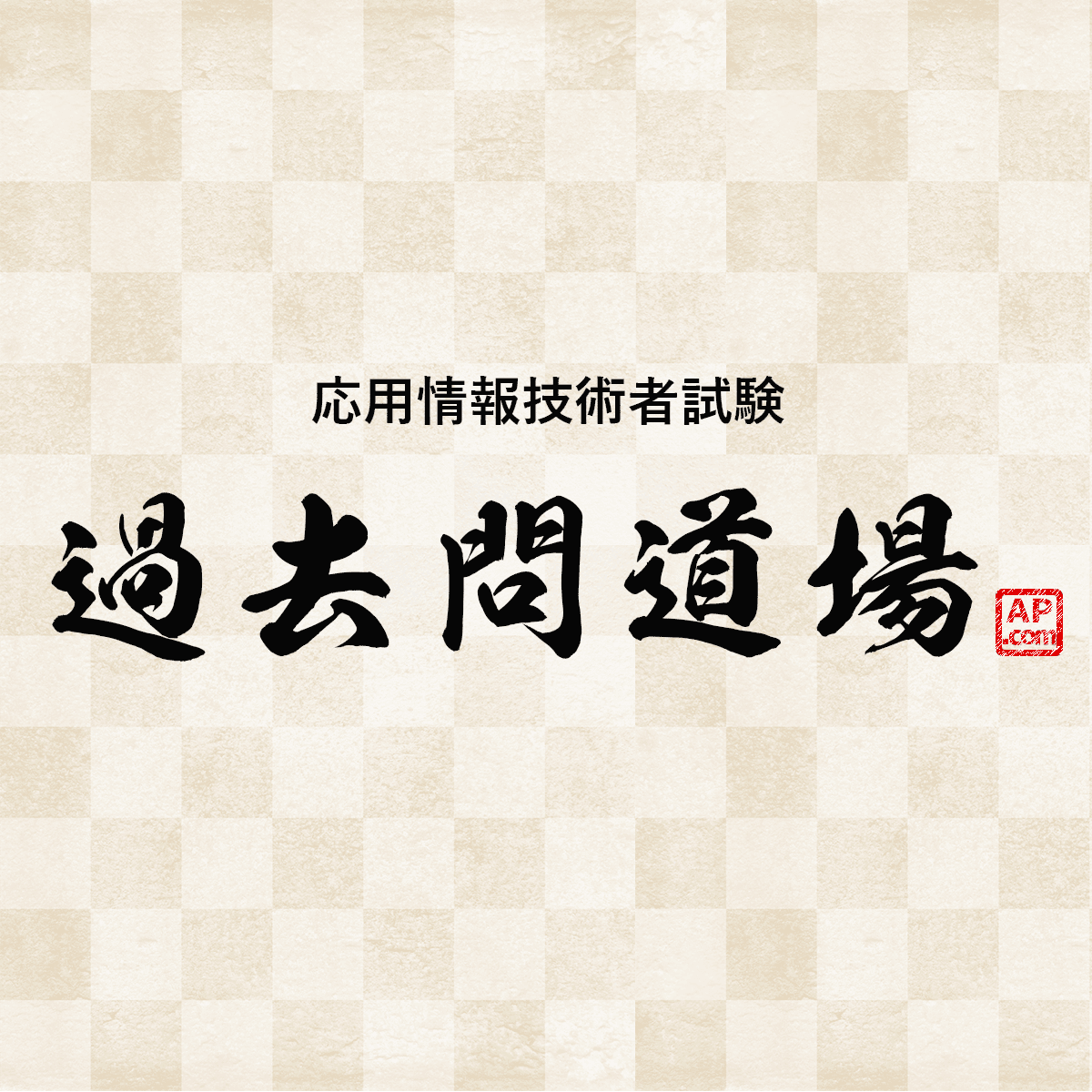はじめに
令和7年の春、初めて応用情報技術者試験を受験した😊
自分の勉強方法を振り返ってみると良い点、悪い点があったので自分なりによかった勉強方法をまとめてみる✨
結論
✅午前は「過去問道場」+「YouTube」+「付箋」がよかった!
✅午後は「どの問題を選択するか」を決めてから過去問を解きまくるのがよかった!
前提
試験概要
応用情報は「午前」と「午後」で2つの試験がある!
午前、午後ともに6割正解すれば合格✨
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 形式 | マークシート(4択) | 記述 |
| 解答数 | 80問 | 5問(1問必須、4問選択) |
| 時間 | 150分 | 150分 |
自分のスキルレベル
「文系?理系?」「IT業界で働いている人か?」「エンジニアか?」など、個人の状況によって参考度合いが変わると思うので、まずは自分のスキルレベルを書いておく。
経験があること
- 理系
- 社会人歴7年目
- 1〜3年目:C++エンジニア
- 4〜7年目:Webエンジニア(フロントエンド多め)
- その他スキル
- 個人的に小規模なWebシステム、モバイルアプリの開発経験あり。
- 普段からITの情報収集をしている。
- 仕事では外注管理を多々している。
経験がないこと
- ITパスポートや基本情報の資格
- 持っていない💦
- データベース
- 独学でSQLを軽く勉強したことがあるくらい💦
- ネットワーク
- 大学で基礎を学んだくらい(ほとんど忘れてる)💦
- 経営系の知識
- まったくない💦
午前の勉強法
結論、「過去問道場」+「YouTube」+「付箋」がよかった✅
過去問道場
どの勉強法を見ても「過去問道場をしよう!」と書かれているが、本当にこのサイトで過去問を解きまくるだけで午前は8〜9割取れるようになった☺️
過去問道場が良かった理由
- 午前は過去問からそのまま出題されたり、類題が出題されたりするため。
YouTubeで苦手分野を補強
過去問を解くだけでは、「元から全く知らない問題」は根本的な理解ができていない感じがして不安だった💦
そこでYouTubeの解説動画を見て、問題を根本から理解できるようにした✅
参考になったYouTube
※基本情報と応用情報で範囲が被っている部分が多いので、基本情報の動画も参考にした。
YouTubeが良かった理由
- 根本的な理解をして、自分で考えられる力を身につけられるため。
- 資格を取るための勉強というより、自分のスキルになる勉強をしたかったため。
覚えられない用語は身近な場所に付箋を貼る
過去問道場をやっていると、何回も間違えてしまう問題が出てくる💦
そういった覚えられない用語はよく見る場所(PC周り、トイレなど)に付箋を貼っておくと自然と覚えられた✨
付箋が良かった理由
- 自分の欠点を自然に補えられるため。
用語まとめ(やらなくてよかった)
これは個人的にはあまりやらなくてもよかったと感じている。
用語まとめを始めた理由
- 応用情報の勉強をしていると山ほど知らない用語が出てくる💦
- 大量の用語を覚えるために片っ端からNotionにメモしていた!
やらなくていいと感じた理由
- 用語が多すぎて見返すのが絶望的な量になってしまった💦
- 用語をまとめなくても過去問道場をしていると自然と覚えられる✨
- やるにしても本当に重要なワードだけメモすればOK✨
午後の勉強法
結論、「どの問題を選択するか」を決めてから過去問を解きまくるのがよかった✅
【前提】いつから午後の勉強を開始すればいいか
筆者は「午前の内容が結構理解できた!」と思ってから午後に取り組んだ。
勉強時間は午前7割、午後3割くらいだった。
理由
- 午後で合格点を取るには、午前の内容をそれなりに理解している必要があるため。
- 逆に午前の内容が理解できていれば午後もそれなりに点が取れるため。
【STEP1】どの問題を選択するか決める
午後は「必須1問(情報セキュリティ)」+「選択4問」に答える必要がある✅
まずは「選択4問」について、以下の流れで5種類に絞った(1問予備がある状態)
流れ
- 好き嫌いせず、全11種類を3問ずつ解く。
- 解いた結果をもとに5種類に絞る。
- まだ5種類まで絞れない場合は、追加で数問やって5種類に絞る。
【補足】どの問題がおすすめ?
筆者もいろいろなサイトを見て、どの問題が簡単なのかな〜と調べた💭
しかしサイトによって評判が違い、自分の肌感とも一致しなかった💦
結局その人の持っているスキルに合わせて選ぶのが一番大事そう!
ちなみに筆者は以下を選んだ☺️
- プログラミング
- システムアーキテクチャ(本番では解かなかった)
- 情報システム開発
- プロジェクトマネジメント
- システム監査
全11種類解く理由
- 「自信がないと思っていた問題」でも意外と点が取れることがあるため。
3問ずつ解く理由
- 何問か解かないと点数がどれくらい安定するか分からないため。
5種類に絞る理由
- 4種類に絞ると本番で他の問題に逃げられなくなるため。
(回によって難易度にばらつきがあるため逃げ道が無いのはリスキー)
- 6種類以上にしても、本番では時間がなくてコロコロ問題を変える余裕がないため。
(自分の場合、問題を変える余裕があるのはせいぜい1回だった)
【STEP2】点が安定するまで過去問を解きまくる
後はひたすら「情報セキュリティ」と「選んだ5種類」の過去問を解きまくった!
(解説が分かりやすく、有名な本なので迷ったらこれを買っておけばいいかも!)
過去問を解きまくる理由
解き方に慣れて、安定して6割以上取れるようになるため。
【よくある疑問】点数が安定しない場合どうすればいい?
何問か解いてみた結果、組み込みシステムの点数が安定しないことに気づいた💦
→スッパリ諦めて、プロジェクトマネジメントにチェンジした✅
【よくある疑問】何回くらい解けばいい?
最終的に追加で3回ずつ解いた。
→得意な問題は8割、それ以外は6割取れるようになった✅
【STEP3】点が安定したら本番と同じ環境で解いてみる
最後は本番と同じ環境で解いて6割以上取れるか確かめる✅
- 問題用紙を印刷する
- 150分計測して解いてみる
本番と同じ環境で解く理由
- 本番は「制限時間」「問題の取捨選択」「長時間の集中力」など独特の難しさがあるため。
【おまけ】実際に受験した感想
午前
- 思ったよりも過去問と同じような問題がなくて焦った💦
- 普段は8〜9割正解できていたが、本番は7割ほどしか正解できなかった💦
- 同じくらい過去問が解けている知人も、本番はぎりぎり6割だったみたい💦
→自分は普段からITの情報収集をしたり、YouTubeで根本的な理解を深めていたおかげで、過去問にない問題もある程度解けたように感じる✨
午後
- 得意な「情報セキュリティ」と「プログラミング」から解いた。
→この段階で結構点を取れていそうだったので、精神的に余裕が生まれた✨
- 開始早々、事前に絞っていた5問を眺めて、難しそうだと感じたシステムアーキテクチャをパスした。
→1問予備を作っておくことで難しそうな問題をパスできてよかった✨
- 150分以内にすべての問題を解くことができた。
→きちんと150分計測して時間内に解く練習をしておいてよかった✨
まとめ
🌟 よかったこと
- 過去問道場とYouTubeの組み合わせは最強!
- 午後は「戦う分野を決める」ことで、勉強効率が上がった!
- 付箋を使ってスキマ時間も暗記に使えた!
🙅♂️ やらなくてよかったこと
- 用語集やまとめノートを作ることに時間をかけすぎるのは非効率だったかも…
よくある応用情報の勉強法と異なるのは「YouTubeで勉強する」という部分かも。
個人的には根本的な理解がしやすく、午前、午後ともに点を伸ばすのにも役立ったのでよければ試してみてほしい✨